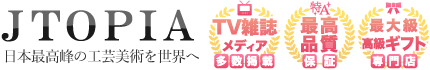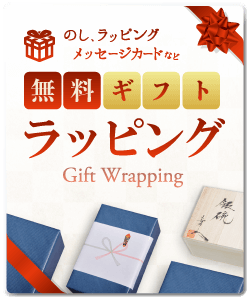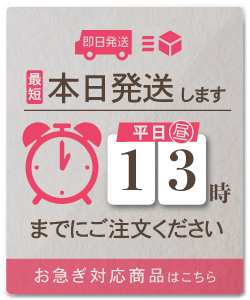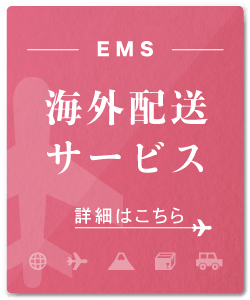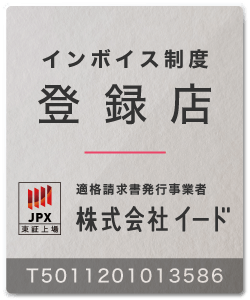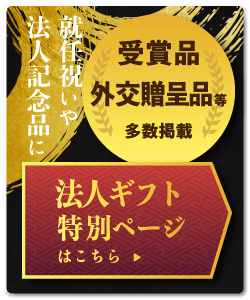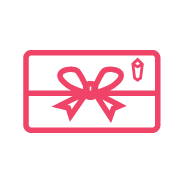Blog
佐賀県は日本で初めて、陶磁器の製法が朝鮮半島から伝わった地域です。1600年代前半に佐賀県九谷地域に伝わったのちに、全国各地へと派生していくこととなります。陶磁器でもっとも長い歴史がある窯元が唐津にありますが、この窯元の代表を務めている第45代当主の「青木龍山」は、1942年に県内初の文化勲章を受章した方です。この作家と青木工房の特徴をここで詳しく見ていくことにしましょう。まず窯元・青木...
もっと見る
どんなに仕事で疲れている状態であっても、美味しい料理やドリンクを頂けば直ぐに幸せな気持ちになってストレスが解消されることがあります。人は食をなくして生きていくことができないため、日々の健康を大切に守っていく意味でも質の高い食事を心掛けていくことが人生をエンジョイする秘訣かもしれません。 上海飯店 そこでおすすめしたいのが佐賀県有田町にある中華料理屋の「上海飯店(シャンハイハン...
もっと見る
有田焼で有名な佐賀県有田町は、日本の磁器発祥の地として有名です。佐賀県有田町の街並みを縦断するように走る県道281号線から少しはいったところには、弁財天を祀る有田・泉山弁財天神社があります。有田・泉山弁財天神社境内の広場には国内でも有数の巨木が立っているのをご存じでしょうか。 有田町の天然記念物 この樹齢一千年の大イチョウは、有田の大公孫樹という名前で地元民に親しまれていて、...
もっと見る
陶器の町として有名な佐賀県有田町の名所「歴史と文化の森公園」をご存知でしょうか。1996年7月から10月まで開催された「ジャパンエキスポ佐賀'96 世界・焱の博覧会」に併せ有田町の歴史・文化のシンボルとして整備され、平成9年4月オープン以来近隣の住民から愛されています。 炎の博記念館 総面積27ヘクタールの敷地を誇る公園には、クラシックなどの音楽イベントが開かれる文化ホールや、...
もっと見る
チャイナオンザパークは、佐賀県有田町にある有田焼の窯元の深川家が運営する深川製磁の工場の敷地内建てられた焼き物のテーマパークです。深川製磁は、1650年から有田で窯に火を灯した歴史ある窯元で、深川家は1894年に作った工芸会社です。深川製磁で作られる陶磁器は、1910年には宮内省(当時は宮内庁)御用達となり、上品で洗練された陶磁器は、天皇家だけでなく、国内外でも愛されてきました。 チ...
もっと見る
本州の西に位置する九州・佐賀県には、紅葉の名所として名高い「黒髪山」があります。標高1,800メートルで九州地域最高峰を記録しており、日本百名山にも数えられる景勝地です。年間約5万人の方々が訪れる霊峰でもありますが、特に10月から11月に掛けてが美しいカエデの色づきを目に出来る季節になっていて、登山客で連日賑わっています。この「黒髪山」は、日本書紀にも登場する由緒のある山です。名前の由来と...
もっと見る
日本は世界有数の陶磁器生産国であり、その技術は古くから伝えられてきました。今や国内だけでなく他国にも愛好家がたくさんおり、日本を代表する産地として、知名度はずいぶん高くなっています。陶磁器の中でも特に有名なものとして瀬戸焼と美濃焼、有田焼の3つがあります。それぞれ伝統文化としても価値が高く、関連する催しものがいろいりと開催されています。そのなかでも有田焼の催しものは非常にユニークであり、毎...
もっと見る韓国の焼き物の歴史は古く、紀元前5000年頃の新石器時代に土器を作っていたとされており、突帯文土器や櫛目文土器などが全土で作られていたとされています。突帯文土器はひものような装飾を施したものが特徴で、櫛目文土器は施斜線の模様を施しています。紀元前後になると、中国からろくろと窯で焼く技術がつたわったことから、瓦質土器が誕生します。瓦質土器は瓦のような特徴があり、硬めの焼き物で灰黒色が特徴的な...
もっと見る
セラミックとは、狭い意味では陶磁器のことを指す言葉として使われていますが、広い意味ではガラスやセメントなど、窯業製品の総称ということで使われています。セラミックスと呼ばれることもあります。 身近な存在 私たちの生活の中でも非常に身近な存在で、パソコンやテレビなどの液晶画面・自動車部品・建物の外壁・屋根などはセラミックで作られています。歯の被せものや人工骨の素材のように医療用の器...
もっと見る
現代は高齢化社会の進捗とともに様々な方が元気でいらっしゃるようになりました。100歳を超えても矍鑠と元気で長生きをしている人がいらっしゃいます。 茶寿祝いとは108歳になった際の長寿のお祝いとなりますが、今回はその由来と意味を紹介いたします。 茶寿祝いの由来 茶の文字は分解すると八十八、十、十になるので合計すると、108になるのが由来です。 還暦や古希などのお祝いには、赤...
もっと見る